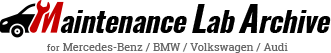― 電気系・オイル系に潜むダメージとその対策 ―
輸入車に乗る醍醐味は、性能・デザイン・乗り味など、すべてが洗練されたバランスにあります。しかし、その魅力を長く保つために欠かせないのが「酸化」に対する理解と予防です。
「酸化」と聞くと、多くの方がまず“ボディのサビ”を思い浮かべるかもしれませんが、実際にクルマに与える影響はそれだけではありません。電気の流れやオイルの性能にも密接に関係し、放置すれば「見えない不調」が積み重なり、ある日突然大きな故障として表面化することも。
今回は、輸入車オーナーとして知っておきたい「酸化によるトラブル」と、その対策について解説していきます。
目次
■ オイルの酸化:エンジンとブレーキを静かに蝕む影
エンジンオイルの劣化は金属疲労と紙一重
エンジンオイルは、エンジン内部の摺動部分を守る潤滑剤であると同時に、冷却・清浄・防錆といった複数の役割を担っています。ところがこのオイル、時間の経過や熱の影響で「酸化」が進行すると、本来の性能が徐々に低下していきます。
たとえば、あるヨーロッパのBMWオーナーの例では、「ロングライフ指定のオイルを信じて交換しなかった結果、5万km手前でピストンリングに異常摩耗が発生。オイル上がりの症状で修理費は30万円以上に」といった声も聞かれます。
酸化したオイルは粘度が変化し、エンジン内部の金属面に油膜を維持できなくなります。最終的にはクランクシャフトやカムに傷が入り、最悪の場合、エンジンブローのリスクも。
対策:5,000〜7,000kmごとの交換を基本に、距離にかかわらず年1回以上の交換を推奨。
ブレーキフルードの吸湿とサビの関係
ブレーキフルードは湿気を吸収しやすい性質を持ち、酸化によって沸点が下がると「ベーパーロック現象(ブレーキの効きが消える)」を招くことがあります。
しかも、フルード内に水分が混入すると、キャリパーやピストンといった鋳鉄製パーツにサビが発生。制動性能の低下だけでなく、修理時の固着・異音といった二次トラブルも引き起こします。
対策:1〜2年ごとの定期交換をルール化。特に車検ごとの交換は必須。



■ 電気の酸化:現代の車に致命的な“流れの悪化”
アースやターミナルの腐食がもたらす微妙な異常
近年の輸入車は、ECU制御・CAN通信など、電気が正しく流れることを前提に設計されています。にもかかわらず、意外と見落とされがちなのが「アースターミナルの酸化」。
たとえば、バッテリー端子やエンジンルーム内のアースポイントに酸化や腐食が見られると、ヘッドライトが暗くなる、始動が不安定、アイドリングが乱れるなど、“なんとなく調子が悪い”現象が頻発します。
実際に、当サイトへの事例内容を見ても「電装トラブルかと思ったら、原因はターミナルの緑青(ろくしょう)だった」という報告が複数寄せられています。
対策:年1回は端子の点検と清掃を。特に冬前や湿気の多い時期は接点復活剤も活用すると安心。


■ 海外でも常識? 酸化対策は“見えない予防整備”
欧州では、日本以上に湿度対策や塩害対策が重要視されており、オイル交換サイクルも「走行より期間優先」が一般的。さらに、バッテリーターミナルを清掃する専用ブラシがガソリンスタンドで販売されるほど、酸化対策は“文化”となっています。
このあたりは「壊れる前に整備する」予防整備の意識が根付いている証拠です。酸化によるトラブルは、目に見える変化が少ないため、ついつい後回しにされがちですが、日常のメンテナンスの中に少し意識を加えるだけで、車の寿命は大きく伸びます。